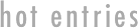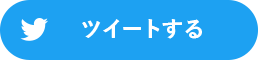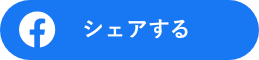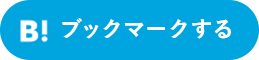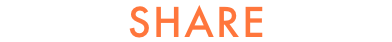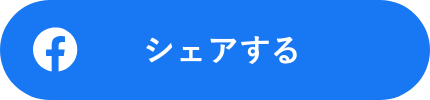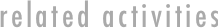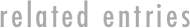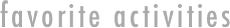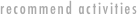わかれば簡単!熱気球の原理を知って空の旅を楽しもう 2024.01.29 熱気球
熱気球って不思議ですよね。翼もプロペラもないのに、あんなに高く空を飛ぶなんて!ゆったりとしたスピードで高度1,000m近くを浮遊し、街や自然のパノラマを優雅に望める熱気球には、ほかのスカイスポーツにはない魅力がたくさんあります。
熱気球の始まりは、フランスのモンゴルフィエ兄弟が暖炉の熱気にあおられた洗濯物を見て、火を燃やしたときに出る煙には空気よりも軽い成分があると発見したことです。そして、温めた空気を集めれば人間も空を飛べると考えて作ったのが熱気球であり、この「熱い空気は冷たい空気よりも軽い」というシンプルな原理が今もそのまま熱気球に利用されています。
空を飛ぶのはちょっと不安…と熱気球未体験の人も、原理を知れば安心ですよね。大空を飛びたくなること間違いなしの、熱気球が浮かぶ原理についてさらに詳しく紹介しつつ、熱気球の魅力についても迫ります!
【目次】
■熱気球の構造ってどうなっているの?
- 球皮(エンベロープ)
- バーナー
- バスケット
■熱気球が浮かぶ原理は?
- 熱気球の操作方法
■熱気球に乗ってみよう!おすすめフリーフライト体験
- 見渡す限りの富良野の雪原を上空から!
- 押し寄せる流氷を空から一望!
【column】熱気球を楽しむ際のポイント!
<<全国で体験できる熱気球ツアーの一覧を見る>>
熱気球の構造ってどうなってるの?
熱気球の原理を説明する前に、まずは熱気球の大まかな構造を紹介しましょう。
温められた空気を包む「球皮(エンベロープ)」

PIXTA
熱気球といえば、まず頭に浮かぶのがこの「球皮(きゅうひ)」。「エンベロープ」とも呼ばれる大きな風船部分です。球皮の大きさと、飛ぶ日の気温によって、持ち上げられる物の重さが決まります。
ロードテープなどの骨組みに、強度が高く、軽いナイロンなどの布のパネルを縫い付けて作られてます。バーナーに近い部分は、燃えにくい特殊な布を使用しています。
球皮の天頂部には、リップバルブ(リップパネル)という排気弁があります。ここからバスケットまで垂れたリップラインと呼ばれるひもを引くと、リップバルブが開いて球皮内の熱気が抜けることで降下できます。
熱気球のエンジン部分「バーナー」

PIXTA
熱気球のエンジンともいえるのが「バーナー」です。球皮とバスケットの間にあり、液化プロパンガスを燃焼させることで球皮内の空気を温めて浮力を作り出します。
熱気球で使われるバーナーは、一般家庭のガスコンロの1,000倍以上の出力があるのだとか。
バーナーは必ず2系統搭載され、1系統が使用できなくなっても、もう片方がすぐ使えるようになっています。
人や燃料などを積む「バスケット(ゴンドラ)」

PIXTA
わたしたちが乗るのが、この「バスケット(ゴンドラ)」部分です。球皮からワイヤーでつり下げられていて、燃料も積み込みます。
材質は籐で編まれたものがほとんど。軽くて丈夫で着地の衝撃が柔らかい、変形しても元の形に戻りやすいという安全性から籐が採用されています。
熱気球が浮かぶ原理は?

PIXTA
熱気球が浮かぶ原理は、ひと言でいえば「熱い空気は冷たい空気よりも軽い」ということ。寒い日に暖房をつけても、温かい空気は部屋の上の方へいって、足元は冷たい空気が溜まったままですよね。
熱気球も球皮内の空気をバーナーで熱することで、中の空気が膨張。暖かい空気は上へ、冷たい空気は下へあふれ、外に押し出されます。そして押し出した空気の分だけ、周囲より空気の密度が低くなり、浮力が生まれるのです。
球皮が水滴を逆さまにしたような形をしているのもポイント!空気の出入り口が狭いので、バーナーで温められた空気は上へ、冷たい空気だけが球皮の下へ移動し、球皮の外へ押し出されます。つまり、効率良く中の空気が温まる形なのです。
「熱い空気は冷たい空気よりも軽い」ことからいえば、寒い日ほど球皮内の空気と外の空気の密度差が得られ、より浮かびやすくなります。
熱気球の操作方法
熱気球の操作は、球皮の天頂部にある排気弁・リップバルブの開閉と、バーナーの火力を調整することで行います。
この方法で操作できるのは上昇と下降だけで、水平方向の操作はまさに“風まかせ”。その日の天候によって毎回違う空の旅を楽しめるのは、熱気球の原理のおかげなんですね!
熱気球に乗ってみよう!おすすめフリーフライト体験
熱気球の搭乗体験には、地上とロープでつなげた状態で一定高度(約30m)を上昇する「係留フライト」と、パイロットの操縦で本格的なフライトを体験する「フリーフライト」の2種類があります。ここでは、北海道で体験できる壮大なフリーフライト体験をご紹介します!
北海道のおへそ!見渡す限りの富良野の雪原を上空から!
空気が澄んでいる冬にこそ挑戦してほしいアクティビティが熱気球です!
北海道のおへそ、富良野を拠点とする「レジャーガイド遊び屋」が主催する“フリーフライト(20分コース)”と“フリーフライト(30分コース)”は、雄大な十勝岳連峰や富良野ならではの広大な雪原を上空から一望できるダイナミックなツアーです。
ゆっくりと上昇しながら視界がどんどん変わっていく体験は新鮮そのもの!条件が良ければ高度1,000mまで上昇し、さらに気温が低ければダイアモンドダストも見ることができます。
「寒さなんて気にしない!ゆっくりと空の旅を楽しみたい!」という方には30分コースがおすすめですよ。
- 北海道富良野市字学田三区4746 レジャーガイド遊び屋・ツアーオフィス
■関連記事
冬の富良野を楽しむ!観光スポットとアクティビティツアー11選
押し寄せる流氷を空から一望!
2005年に満を持して世界自然遺産に登録された自然の宝庫、知床。
知床の魅力は何といっても息をのむような美しい自然景観の数々ですが、これらを上空から見ることができる夢のようなツアーが「知床ツーリスト主催」の“熱気球フリーフライト”です。
特に冬場のフライトでは、オホーツク海に流れ着く見渡す限りの流氷を一望できるなど、気温の低さが可能にする自然の造形を上空から堪能できます。熱気球体験は、寒さ対策だけバッチリしておけば装備もテクニックもいりません。
視点を変えて知床の魅力を感じてみたい人にはおすすめのツアーですよ!
- 北海道斜里郡清里町向陽282 清里イーハトーヴホステル
■関連記事
【世界自然遺産】知床の冬の観光・流氷の絶景スポット8選
熱気球を楽しむ際のポイント!

風まかせに空を舞う優雅な熱気球は、その性質ゆえに天候に左右されるアクティビティです。
まず、風速。競技やツアーによって条件は多少変わりますが、通常は風速3m以上になると中止とされることが一般的です。風速3mとは木の葉を揺らす程度の穏やかな風ですが、それでも空の旅では危険と判断されるそう。このことから熱気球のツアーは風が弱まる早朝開始が基本なので、体験する土地での前泊が必要となります。
次に気温。そもそも熱気球は気球内部の温度と外気の温度差で浮力が生まれ飛ぶことができます。つまり、気温が低いと浮力が大きく、気温が高いと浮力が小さくなるので、気温が低い冬こそ好条件になります。
ただでさえ上空は地上に比べて気温が低いですが、それが冬となると寒さも格別。熱気球のオンシーズンともいえる冬場のフライトでは寒さがつきもの。防寒対策はもちろん、発着場で雪道を歩くこともあるため、足元はスノーブーツなどがおすすめです。
視界が悪い状態(雨・雪・霧・日没後)や、上下にコントロールができなくなる上昇気流があっても飛行ができないので、フライトの確率はだいたい6割程度となっています。確実に体験をしたいのであれば、複数日を候補として抑えておくとよいでしょう。
北海道で熱気球体験を楽しもう!
北海道の中でも特に気温が低く晴れの日が多い道央や道東は、まさに熱気球にとって理想のフィールドです。スノースポーツ以外の北海道の冬のアクティビティとして、ぜひ熱気球にチャレンジしてみませんか。
アウトドアレジャーの専門予約サイト「そとあそび」では、熱気球をはじめ北海道でおすすめのアクティビティツアーを多数紹介しています。ぜひチェックしてみてください!
(編集部注*2015年10月20日に公開された記事を再編集したものです)
※掲載されている情報は公開日のもので、最新の情報とは限りません。
最新記事

ピックアップ
![]()
マンスリーチョイス
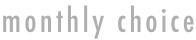
その他の記事
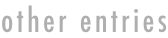
人気の記事