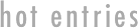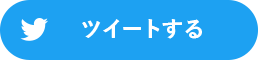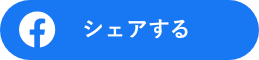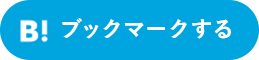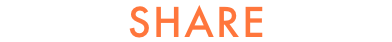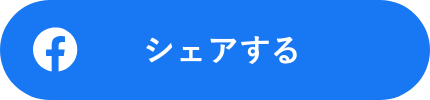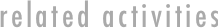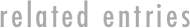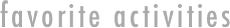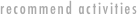沖縄を楽しむならカヤックでマングローブ探検!その魅力をエリア別ツアーで徹底解説 2024.08.20 カヌー・カヤック 沖縄県
日本では沖縄県と鹿児島県でしか見られないマングローブ。河口付近に群生するマングローブ植物を観察するには、水上をゆっくり移動できるカヤックが最適です。
本島から離島まで、マングローブが点在する沖縄県では、カヤックでのマングローブ探検が大人気!亜熱帯の密林を進む非日常の感覚は、本州以北では得られません。
今回は沖縄県で体験できるマングローブカヤックの魅力と、エリアごとのおすすめツアーを紹介!沖縄を訪れるなら、ぜひ挑戦してみてくださいね。
【目次】
■マングローブとは?
■沖縄のマングローブで探そう!珍しい生きもの
- 1.マングローブ植物
- 2.ミナミトビハゼ(トントンミー)
- 3.シオマネキ
- 4.ヤエヤマヒルギシジミ(シレナシジミ)
- 5.カワセミ
- 6.リュウキュウアカショウビン
■億首川|本島・金武町
- 1歳からOK!家族に人気のグループ貸切ツアー
- 楽しく自然を学べる!恩納村集合のツアー
■比謝川|本島・嘉手納町
- カヤックから絶景サンセットを独り占め!
■慶佐次川|本島・東村
- 短いツアー時間で手軽に楽しめるマングローブ探検!
■羽地内海|屋我地島
- マングローブ散策や無人島上陸…見どころいっぱいのツアー
■宮良川|石垣島
- 頼もしいガイドと一緒に冒険気分でカヌーの旅を楽しもう!
- ドラマチックなシーンをめぐるスペシャルなカヤックツアー!
■仲間川|西表島
- 上陸してジャングル探索を楽しもう!
- ナーラの滝を目指して!カヤック&ジャングルトレッキング
■浦内川|西表島
- マングローブ植物をじっくり観察!
<<沖縄県で体験できるカヌー・カヤックツアーの一覧はこちら>>
マングローブとは?

PIXTA
「マングローブ」とは、熱帯や亜熱帯地域の河口などで、海水と淡水が混ざり合う“汽水域”に群生する植物の総称。日本では沖縄県と鹿児島県に自然のマングローブが存在します。
世界各地の熱帯・亜熱帯地方に自生しており、適応温度は15℃~35℃、湿度は70%以上が理想。寒さに弱いのが特徴で、5℃以下の日が続くと急激に枯れやすくなってしまいます。
また、マングローブには魚類や甲殻類、哺乳類、鳥類、昆虫類など、多種多様な生きものが生息。そのため、マングローブは“命のゆりかご”とも呼ばれており、生態系を支える大切な役割を担っている点も重要なポイントです。
■関連記事
沖縄のマングローブカヤックならここだ!おすすめツアーまとめ16選
沖縄のマングローブで探そう!珍しい生きものたち
マングローブ周辺には、普通の森では見られない珍しい生きものがたくさん生息しています。遭遇確率が高いものから激レアなものまで、動植物問わずその種類はさまざま。その中から探検する際にぜひ探してみてほしい、6種類の生きものを紹介します。
1.汽水域で生きるための特殊な機能を持つ「マングローブ植物」

PIXTA
日本に生息するマングローブ植物は5科7種。沖縄県と鹿児島県にのみ生息していて、沖縄県にはオヒルギ・メヒルギ・ヤエヤマヒルギ・ヒルギモドキ・ヒルギダマシ・マヤプシキ・ニッパヤシのすべてが分布。中でも西表島は、全種類のマングローブ植物に唯一出会えるエリアとして知られています。
マングローブ植物が育つのは、海水と淡水が混ざり合う汽水域。塩分を吸収しても枯れないのは、葉に塩分を溜めて黄色い落ち葉として排出できるから。また、波に打たれても倒れないのは、タコの足のようだったり、板のようだったりする不思議な形の根がしっかりと支えているおかげ!生き抜くための特殊な機能が、たくさん備わっています。
種類によって塩分の耐久性は異なり、環境によって住み分けをしています。塩分に強いヒルギダマシ・マヤプシキ・ヤエヤマヒルギは海側、メヒルギ・オヒルギは陸側といった具合です。
ぜひカヤックで、不思議なマングローブ植物の生態をじっくり観察してみてくださいね。
2.大きな目玉が目印!干潟で飛び跳ねる魚「ミナミトビハゼ(トントンミー)」

PIXTA
沖縄県では“トントンミー”と呼ばれ親しまれている「ミナミトビハゼ」は、体長10cmほどのハゼ科の魚。
日本では鹿児島県の種子島以南に生息し、泥のある干潟でよく見られます。魚ですが陸上で過ごす時間が長く、胸ビレを使って移動したり、飛び跳ねたりするのが大きな特徴です。
潮が満ちてくると水を避けるように移動し、ときにはヒルギの枝などに登って気持ち良さそうに休憩する姿を見られることも! 飛び出た大きな目玉と、黒い帯状の模様を目印に探してみましょう。
3.片方だけ大きなハサミを振って求愛する「シオマネキ」

PIXTA
カニの一種である「シオマネキ」は、オスのみ片方のハサミが極端に大きいという特徴を持っています。
大きなハサミを振る“ウェイビング(Waving)”という求愛行動が、早く潮が満ちるのを招くように見えることから“潮招き”という名前が付いたそう。漢字では「潮招」「望潮」と書かれ、春の季語にもなっています。
日本では10種類ほどが干潟や砂浜で見られます。沖縄県には、オキナワハクセンシオマネキやベニシオマネキなど、カラフルな8種が生息。
ハサミが大きい脚は、“利き腕”のように右だったり左だったりと個体差があり、横長の甲羅の幅は20〜40mmと種類によって異なります。同じ干潟で数種類のシオマネキを見られるほど、マングローブではポピュラーな生きもの。ぜひたくさんの種類を探してみましょう!
4.大きさは10cm以上!日本最大のシジミ「ヤエヤマヒルギシジミ(シレナシジミ)」

PIXTA
奄美諸島以南に生息する「ヤエヤマヒルギシジミ」は、大きいもので30cmにもなる日本最大のシジミ。沖縄県では“シレナシジミ”や“マングローブシジミ”と呼ばれています。
マングローブの泥の中に生息していますが、マングローブは干潮時に干潟になり、水がないと生きていけない貝類には過酷な状況に。
そこでヤエヤマヒルギシジミは殻を大きくして、たくさん水を溜められるよう進化したのだそう。生存のために殻は大きくしたものの、身はそのまま小さいというギャップがかわいらしい生きものです。
5.翡翠色の背と長いくちばしが美しい「カワセミ」

PIXTA
川や湖などの水辺に住む「カワセミ」。日本各地に生息しており、沖縄のマングローブでも見られます。
カワセミは漢字で「翡翠」とも書く通り、緑がかった青色の背と長いくちばしが特徴の鳥。胸と腹はオレンジ色、足は赤色とカラフルで美しく、古来から“飛ぶ宝石”や“渓流の宝石”と称されてきました。
くちばしはオスは黒く、メスは下だけ赤いので、雌雄の区別は簡単。水面に飛び込み、長いくちばしで魚や昆虫を捕らえます。高い鳴き声がカワセミを見つけるヒント!声が聞こえたら、その方向をじっくり観察してみましょう。
6.“赤い弾丸”と呼ばれる珍しい鳥「リュウキュウアカショウビン」

PIXTA
先に紹介したカワセミの仲間・アカショウビンの亜種である「リュウキュウアカショウビン」。夏に奄美大島以南に渡来する渡り鳥です。
くちばしや足は鮮やかな赤色、背は紫色、腹はオレンジ色と赤系の体色をしており、一直線に飛ぶ姿から“赤い弾丸”の異名を持っています。
全長は27cmとカワセミより大きく、赤い体はマングローブの中でひときわ目立ちますが、今回紹介した中ではレアな生きもの。石垣島と西表島では遭遇率が上がります。「キュロロロロロロー」という鳴き声が聞こえたら、周囲を見渡してみましょう。
4種類のマングローブ植物と多様な野鳥に出会える「億首川」|本島・金武町
沖縄本島中部の東海岸に位置する国頭郡(くにがみぐん)金武町(きんちょう)。そこを流れる億首川(おくくびがわ)は、本島で唯一、4種類のマングローブ植物が自生しており、野鳥が多いことでも有名です。
那覇空港からの所要時間は沖縄自動車道を利用して車で約70分、人気の観光スポット「万座毛(まんざもう)」から約25分、青の洞窟で有名な「真栄田岬(まえだみさき)」から約35分と、沖縄旅行の際に立ち寄りやすいスポットです。
1歳から参加OK!家族に人気のグループ貸切ツアー
億首川で「アンダゴ」が開催する“マングローブのカヤック探検ツアー”は、なんと1歳から参加OK!小さい子供連れでの旅行は何かと気を使うことが多いですが、こちらは1グループ貸切制で気兼ねなく参加できますよ。
マングローブの葉を手に取ってさわってみたり、シオマネキやトントンミーなどの生きものを観察したりしながらゆったりとクルージング。子供にとってもカヤックの揺れは心地良いかもしれませんね。
ツアーの途中では、マングローブの中にあるデッキに上陸して、ドリンク&おやつタイムも!所要時間は約2時間と短いのでファミリーでも無理なく楽しめ、観光の合間に体験するのにぴったりのツアーです。
- 沖縄県国頭郡金武町金武11818-2 自然体験学習施設「ネイチャーみらい館」
■関連記事
【ご家族向け】沖縄で子供とマングローブを見るならカヤックで決まり!
夕方や夜のカヤックも楽しめる「比謝川」|本島・嘉手納町
本島中部の嘉手納町(かでなちょう)を流れる比謝川(ひじゃがわ)。本島の川では最大の流域面積を誇り、河口は西海岸に面しています。干潮時でもカヤックができる比謝川では、サンセットやナイトツアーも開催されているのが特徴。
那覇空港から車で約60分、那覇市内からも40〜50分と市街地からとアクセスも良好です。
カヤックから絶景サンセットを独り占め!
「カヤックイーズ」が開催する“サンセットツアー”は、東シナ海へ沈む夕日をカヤックから眺められるロマンチックな内容!日が沈む前にマングローブに入り、ヤドカリや水辺に集まる鳥たち、マングローブなどの生きものを観察します。
日没間近になったらベストポジションに移動してスタンバイ!どんなサンセットが見られるのか、波に揺られながらワクワクして待つ時間もまた、このツアーならではの楽しさです。
カヤックイーズでは、明るい日中に生きものをじっくり観察できる“マングローブツアー”、暗闇のマングローブをライトで照らしながら探検する“ナイトツアー”も開催しているので、目的に合わせて選んでみてはいかが。
- 沖縄県中頭郡嘉手納町字水釜566-15 カヤックイーズ
本島で2番目に広いマングローブ林が広がる「慶佐次川」|本島・東村
本島北部の東、太平洋に面する慶佐次(げさし)湾。そこへ流れ込む慶佐次川の河口部約1kmほどにマングローブ林が広がっています。
本島で2番目に広いマングローブ林では、メヒルギやヤエヤマヒルギ、オヒルギを観賞可能。やんばる国立公園に属し、国の天然記念物にも指定される人気のスポットです。
那覇からは車で約1時間40分、名護からは約40分。“やんばる(山原)”と呼ばれる北部へ足を延ばすなら、ぜひ立ち寄ってみてはいかが。
短いツアー時間で手軽に楽しめるマングローブ探検!
「やんばる.クラブ」では、マングローブ林の中をツーリングできる“マングローブカヤック1時間半ツアー”を開催。所要時間が約1時間半と短めで、観光の合間にちょっとだけ自然体験してみたい人にぴったりなツアーです。
マングローブではふれられるほど木々の近くまで寄り、植物や生きものをじっくり観察。何か見つけたときはどんどんガイドに質問しましょう。ガイドの詳しい解説で、より深く慶佐次川の自然について知ることができます。
ツアー終了後には、広々したシャワー室で温かいシャワーを浴びることができるのもうれしいポイント。温水シャワーで汚れも疲れもサッと流して、そのまま周辺観光に出かけちゃいましょう。
- 沖縄県国頭郡東村慶佐次155 やんばる.クラブ
■関連記事
沖縄・慶佐次のマングローブカヤックで見られる生物まとめ
最新記事

ピックアップ
![]()
マンスリーチョイス
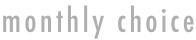
その他の記事
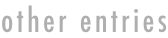
人気の記事